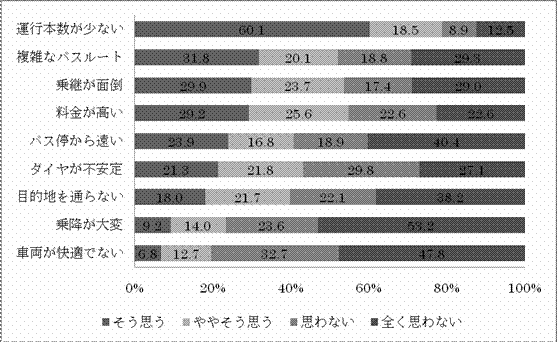
自治体の行うバス(コミュニティバス)計画作成のポイント(抄)
第1章 コミュニティバスに関してよくある誤解
平成18年以来バス110番で全国各地の話をお聞かせいただいて、共通な誤解があることに気がついた。本論に入る前にまずコミュニティバスを計画するうえで陥りやすい勘違いを述べてみたい。ここで気がついた読者は関連する項目を見ていただければ幸いである。
(1)廃止だから代替を用意する必要がある
コミュニティバスの多くが撤退後の路線バスの代替である。バス業者が撤退すれば、そのまま廃止になるケースは少なく地元住民や議員から復活の要望が出され、同じ路線、同じダイヤで組んでしまうであろう。しかし人が利用しないからバス業者が撤退を表明したのであり、必要があるかどうかまず調べなければならない。誰が何の目的でどこまで乗るバスなのかコンセプトを明確にする必要がある。バス路線の沿線の集落の人口や人口構成も年々変化しているため、以前からあるバスの役割が終わっていたりするケースもあるだろう。
またバスにこだわる必要はない。目的は住民に移動の手段を提供することであるから、場合によってはタクシーの補助でもいいし、過疎地有償輸送のような形態でもいいと思う。目的が明らかになったら、一番コストのかからない効率的な輸送手段を選択すべきであり、バスを残すことが目的ではない。(⇒第3章計画作成の基本的方針)
(2) 1人でも多く乗ればいい、採算が取れなければだめ
いざ自治体がバスを運営しだすと、利用者が1人でも多い方が役立っていると思い、多く乗せることばかり考える自治体がある。空で走っているバスのことを「エアバス」と言う人もいたが無駄の象徴である。だから心情的には1人でも多く乗せることを目的にするのは理解できなくはない。乗らなければ企画した担当者の努力不足だったと思ってしまう。バス路線を開設したが乗らないとこぼす担当者は多いが、では何人乗る予定だったかと聞くと、とたんに黙ってしまう。民間のバス会社であれば、利潤を得ることが目的であるから、1人でも多く乗ってほしいだろう。もし十分儲かるなら自治体が運営するのではなく民間に譲るべきである。そうでなければ民業圧迫になってしまう。何人乗ったらいいのかは、どのような人をどこからどこまで何の目的で運ぶのかを明らかにし、需要予測を立てなければわからない。すなわち1日何人運ぶ予定だったかが明らかでなければ、成功とも失敗とも評価できない。バス路線沿線に1人しか住んでいなければ、乗るのはたった1人であるし、それで目的を達成しているのである。逆にそこそこ乗っていても、潜在的にはもっと乗るはずの計画であれば目的を達していない。採算の議論も同様で儲からないとだめなら全国ほとんどのコミュニティバスは運行できない。採算性を達成するのではなくある目的を達成するために最も効率的な手段を選ぶことが必要である。自治体はバス会社ではないのである。(⇒第8章 需要予測の方法)
(3) 小さい車両なら効率的
大きなバスに数人の乗客では確かにスペース的にもったいないし、多くの燃料を消費し無駄だと思うのは心情である。ムーバスが小型車両を使っているので真似をしてみたい気にもなる。しかしバスの運行経費の大半は人件費であり、燃料代の差はあまり全体に響かない。また、大型バス、小型バスの燃費はそれほど違わないのが実情である。既に小型のバスがあるならまだしも新たに小型のバスを購入するにはそれなりの予算が必要であるので、既存の大型バスを利用した方が経済的である。ただし小さい車両でないと入れないような狭い道に路線を通したいときには小型車両は有効である。
(⇒第5章新規路線の計画方法(6)バス車両)
(4)多目的に使いたい
どうせ役所の金を使ってするなら少しでも色々な目的に利用したいと考えるのはもっともである。買い物、通勤、通学、通院、観光や環境問題まで言い出せばきりがないであろう。だが目的に応じてルートやダイヤは違ってくる。時間一つを考えても買い物は平日、休日の昼間の時間のニーズが高く、通勤・通学は平日の毎日朝晩の利用が多い。また通院は朝が早いが毎日行くものではない。観光になると休日にニーズがあり客は外部の人で行く先は住民が殆ど行かない観光地である。このように多目的になればなるほどルートやダイヤを増やさなければならない。だが予算の制限があるので同じ金額であれもこれもと盛り込んでしまう結果、サービスレベルの極めて低い中途半端なバスシステムができ、結局誰も利用しないことになる。(⇒第3章 計画作成の基本的方針(1)目的の明確化)
(5)循環にしなければならない、デマンドにすればいい
コミュニティバスは循環で100円というステレオタイプな考えの担当者が多い。ムーバスの成功でコミュニティバスは武蔵野市のムーバスそっくりにしなければならないと固く信じ込んでいるように思える。だから何が何でも循環にしなければならないと、複雑な路線を描いてしまう。デマンドバスが他市町村で成功していると、デマンドバスなら交通問題を解決してくれるものと期待してしまうことは多いであろう。
だが循環バスにせよデマンドバスにせよ、どこにでも適用できるものではない。ムーバスが循環にしたのは、運行している吉祥寺周辺は道が狭く一方通行が多かったので必然的に一方通行の循環にせざるをえなかったこともある。またムーバス第1号路線の吉祥寺東循環は1周4.2km、25分と短いために一方向循環でも便利で100円も手ごろな値段なのである。これを理解せず形だけを真似ると極めて使いにくいバスになって結局誰も乗らなくなる。
デマンドバスも都会のように需要の多いところではお客を乗せるためにあちこち寄り道をしなければならず、時間がかかって利便性は低下する。反対にあまりにも需要が低いところでは乗合が成立せずタクシーと同じになってしまう。よそが成功しているからと言って決して無批判に真似てはならない。(⇒第5章新規路線の計画方法、第6章デマンドバスの計画方法)
(6) 公共施設を結べばいい
コミュニティバスを循環バスと考えている人が多いが、役場、公民館、図書館、社会福祉センター、公会堂など公共施設を循環させる路線が少なくない。役所の金で運営するのだから、公共的な施設を回るのは当然で、しかもスポンサーである役所には必ずよらなければならない、民間の施設に立ち寄るのは公平性の点から問題がある、などと考えているのかもしれない。だが公共施設の「オリエンテーリング」を行うのは役場の職員くらいである。それも役場の職員は役場の車で移動するからバスには乗らない。つまり誰も乗らないバスになるのである。コミュニティバスは「役場に行くのは便利だが、それほど必要はない」との声も聞く。役場に行くのは何かの手続きで住民票を取りにいったり、最近は役所がお金をくれたりするので行く機会はないわけではないし行けなくなると不便である。しかし毎週必ず行かなければならない所でもなく、ニーズはあるが利用頻度はかなり低いといえよう。コミュニティバスはまず乗客のニーズを調べてから路線を組むべきである。(⇒第8章 需要予測の方法)
(7) 自家用車から転換させたい
最近は地球温暖化の問題が大きくクローズアップされている。2009年のコペンハーゲンでの会議(COP15)では日本が1990年比で2020年には25%減らすと公約をした。運輸部門の二酸化炭素排出量の約9割が自動車からという現実を踏まえても、自家用車の利用を抑制しようという動きは日本にも押し寄せている。コミュニティバスで自家用車からの転換を図り、交通問題と環境問題を一挙に解決するというのは一見いいアイデアのように見える。
ところが自家用車からバスへの転換は至難の業である。成功したところは筆者が不勉強のせいか聞いたことがない。自家用車を持っていればいつでも、どこでも行ける自由度がある。しかし大都市を除けば公共交通が高いサービスレベルで運行している地域はなく、簡単に代替できないのである。役所のなけなしの予算で走るコミュニティバスは自家用車に対抗するには極めて非力と言えよう。盛岡市で筆者が行った調査では高齢運転者の公共交通に関する不満で最も大きかったのは運行頻度の低さであった(図―1)。別の言い方をするなら自家用車から転換させるには非常に高いバスのサービスレベルが求められるのである。それだけの予算が組めるのであろうか。自家用車からの転換はガソリンを1リットル1000円にする等かなりドラスチックな政策をとらなければ不可能である。自家用車からバスへ転換させたい気持ちは理解できるが、コミュニティバスだけでの実現は不可能に近い。(⇒第3章計画作成の基本的方針)
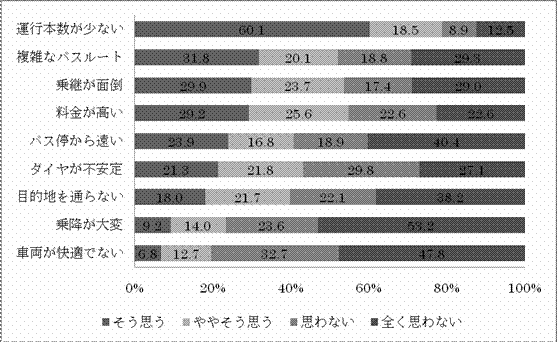
図−1 高齢運転者のバスに対する不満
(8) 地元が利用するというから走らせる
路線バスが撤退するというと、地元の住民や議員から存続の要望が出てしぶしぶ市役所が引き受けるというのが実情ではないだろうか。しかし地元からの要望をよく分析する必要がある。まず要望している人が本当に乗るかどうかである。法律で地域公共交通会議が制度化されて筆者が出席する機会も少なくないが、試しに「この中で会場までバスで来た人はいますか」と聞くと大概沈黙してしまう。必要だと言っている人が乗るとは限らない。
地元の意向を鵜呑みにすると過大な予測となることが多い。自家用車が運転できる人がバスに転換することは稀であり、地元の要望の中にはバス路線がないと嫁が来ないからという意見もあるのである。(⇒第8章需要予測の方法(2)利用意向から推定(アンケート調査))